「勉強を始めたいけど、気づいたらスマホを見てる…」
「机には向かうけど、やる気が湧かずに時間だけが過ぎていく…」
社会人になると仕事の疲れや誘惑も多く、勉強に取りかかるまでが長くなりがちですよね。
学習はモチベーションに頼らずにまず習慣化させることが大事ですが、習慣化に繋げるまでの最初の一歩に苦労するものです。
私は朝活を3年以上続けていくつか資格も取ってきました。
はじめの頃はモチベーションで乗り切っていましたが、ふとした時に気持ちが切れて、「起きてもしばらくスマホを見て起きれない」という時期がありました。
この記事では、「なかなか始められない」人が今日から実践できる小さな工夫やきっかけ作りを、私自身の経験をもとにお伝えします。
なぜ勉強を始めるまでが長くなってしまうのか
そもそも勉強をやらないといけないという気持ちはあるのに、始めることができないのでしょうか。
その理由を3つの視点から考えてみます。
1. 完璧主義による「始めるハードル」の高さ
スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエック氏は「固定マインドセット」を持つ人は失敗を自分の能力の低さと捉えて挑戦を避ける傾向があると述べています。
完璧にやらなければ意味がない、という思い込みが「最初の一歩」を極端に重くしているのです。
そのため、机に向かう前から「しっかりやらなきゃ」「失敗したくない」と無意識にプレッシャーをかけ、行動が先延ばしになってしまいます。
2. 環境が整っていない
勉強を始めるには「集中できる場所・時間・道具」が整っていることが重要です。
周囲に気が散るもの(スマホ、テレビ、通知音など)があったり、机が散らかっていたりすると、それだけで集中モードに入れず、行動が遅れがちになります。
特に家では「勉強モードと休憩モードの境界」が曖昧になりやすく、無意識のうちに「くつろぎ」の気分が残ってしまい、切り替えができないまま時間だけが過ぎていってしまいます。
3. 疲れやストレス
疲れているときや精神的にストレスがかかっているときは、集中力・意欲・判断力が著しく低下します。
このような状態で「勉強しなきゃ」と思っても、身体が拒否反応を起こし、自然と後回しになってしまいます。
とくに社会人や学生のように日常的にタスクや人間関係のストレスを抱えている人にとっては、始める前に回復時間が必要です。
勉強を始めるきっかけづくり
勉強が始められない理由を考えてみたところで、実際に行動できるようなきっかけを作ってみましょう!
動く
まずは手を動かす
考えるよりも先に思いついたことを行動に移すと、気持ちが行動に合わせようと脳が働きかけてくれます。
結果的に始める前よりも深く考えることができるようになり、勉強へ向けた切り替えができるようになります。
本を読むより問題を解いてみるなど、実際に手を動かしてみる方がより効果的です。
SNSで勉強開始を宣言する
他者とのつながりやコミュニケーションはモチベーションを向上させることができます。
身近に家族や友人がいればいいですが、そうでない場合はSNSを活用して勉強をやるという宣言をすることで、勉強をしないといけないという気持ちになってきます。
SNSを活用していると人と繋がったり、もっと頑張っている人を見かけたりするので、一層やらないといけないという気持ちになります。
外出の準備をする
例えば朝から勉強する場合、パジャマのままだと気持ちが入らないと思います。
顔を洗って着替えて外出する準備まですることで、自宅モードから外出モードへ気持ちが切り替わり、気持ちが入ります。
合図を決める
音楽を聴く
好きな音楽を聴くとドーパミンの分泌を促し、ストレスの減少やリラックスをすることができます。
気持ちが落ち着いた後に勉強を開始するとすっと気持ちを切り替えることができます。
また、勉強を始める前に毎回同じ音楽を聴くようにすると、その曲を聴いただけで勉強モードに切り替わるようになるのでおすすめです。
ただ、勉強中に音楽を聴くことは効率を下げてしまうので、開始する前までにしておきましょう。

瞑想を行う
瞑想はストレスや不安を取り除く効果があるだけでなく、集中力を高める効果があります。
目を瞑って、呼吸を意識するだけで段々と深く潜るような感覚になるのがわかるはずです。
勉強開始前に行うことで、余計な感情や気持ちが取り除かれ、勉強に気持ちが入りやすくなります。
整える
片付ける
いざ、勉強を開始しようとしても目の前にたくさんの書類があったり、漫画などの誘惑があったりするとついそちらに手が伸びてしまいます。
あらかじめ勉強するための環境を整えておいて机に向かうと気持ちを切り替えやすくなります。
机周りを片付け、必要なものだけを用意するというだけでなく、作業用の専用スペースを確保することも大切です。
作業スペースに向かうという行為が勉強の場として脳に認識されやすくなり、習慣化につなげることができます。
場所を変える
自宅だと勉強できない場合は場所を変えて勉強を始めてみましょう。
近くのカフェやファミレスに出かけると自然と気持ちが変わっていき、勉強に向かうことができるはずです。
また、カフェやファミレス以外にも、図書館などの公共スペースを使用すると同じように勉強している人がいるので、気持ちが高ぶり勉強に集中することができます。

スマホは見えない所に
誘惑となることは物理的に絶ってしまいましょう。
勉強中についつい手が伸びてしまうのであれば、遠くに置いておくことで目の前のことをやるしかなくなります。
iPhoneであれば集中モードを使用したり、スマホの使用を制限するアプリや勉強用のアプリを活用したりすることで勉強する環境づくりのサポートをしてもらうことも検討したいです。

習慣に変えるための工夫
せっかく勉強を始められるようになっても、それがすぐに終わってしまうと勿体ないです。
勉強を習慣づけすることで、長く継続することができます。
朝活・昼活でタイミングを固定する
朝や昼の時間を活用し、毎日同じタイミングで勉強を行うことによって習慣づける方法です。
特に朝の時間帯は頭もスッキリしていますし、周りも静かな環境なのでおすすめです。
私は3年以上朝活を続けていますが、今では 朝起きる = 作業を始める が習慣づいています。
始め方や継続するコツをまとめていますので、ぜひ読んでみてください。
確実に続けていくためには「昼活」もおすすめです。
SNSやアプリで「記録する」
勉強内容や時間をSNSやアプリに記録することで、モチベーションが継続しやすくなります。
積み重ねが目に見えることで、「せっかくここまでやったんだから今日も少しだけ…」という意識が生まれます。
また、続けていくことによって達成感も倍増します。
さいごに
仕事、家事、育児などをこなしてあっという間に過ぎる1日に疲れてしまい、時間ができても気づいたら朝だったという日々を過ごした経験のある方は多いと思います。
その少しの時間を勉強するモードに切り替えるために、今回紹介した方法を試して頂ければと思います。
コツコツ続けているとそれが習慣化され、モチベーションに頼ることなく継続的に勉強ができるようになってきます。
よりよい未来のために、共に第一歩を踏み出しましょう!
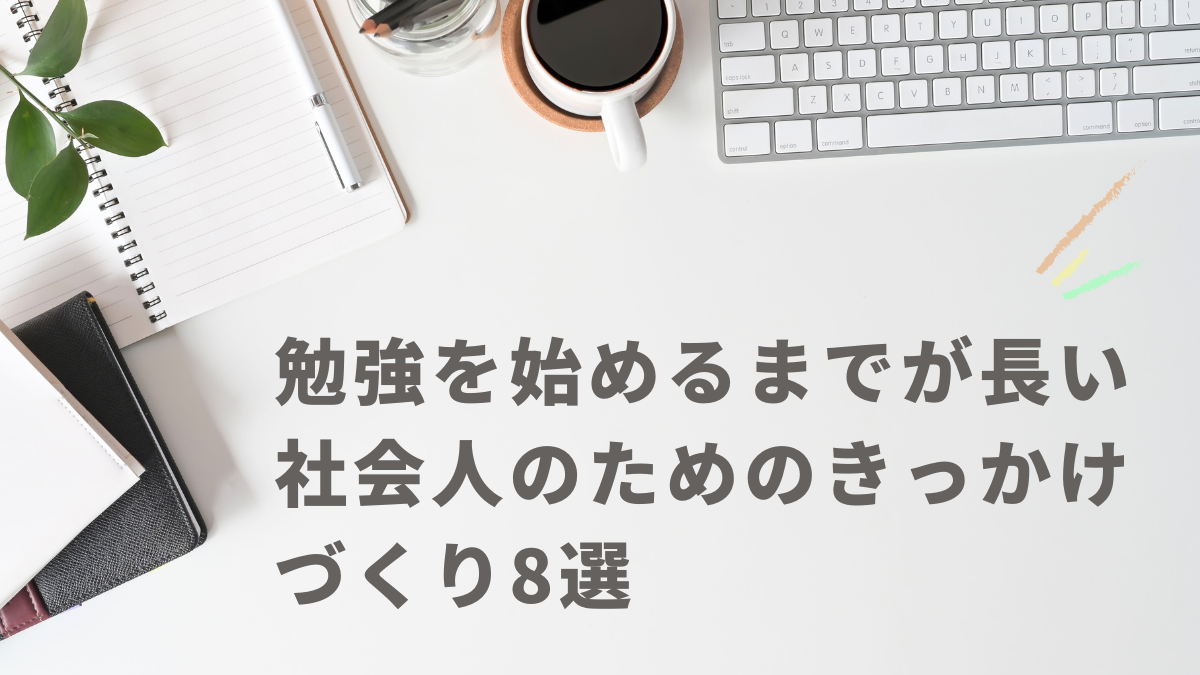
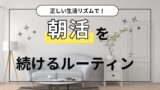
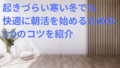

コメント